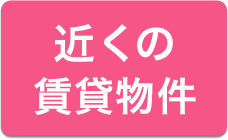「山都通潤橋IC」から直線距離で半径1km以内の観光スポット・旅行・レジャーを探す/距離が近い順 (1~4施設)
①施設までの距離は直線距離となります。目安としてご活用ください。
②また ボタンをクリックすると山都通潤橋ICから目的施設までの徒歩経路を検索できます。
ボタンをクリックすると山都通潤橋ICから目的施設までの徒歩経路を検索できます。
-
周辺施設山都通潤橋ICから下記の施設まで直線距離で846m
通潤橋
所在地: 〒861-3661 熊本県上益城郡山都町長原
- アクセス:
桜町バスターミナル-通潤山荘・田迎・御船経由「「通潤山荘」バス停留所」から「通潤橋」まで 徒歩3分
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 通潤橋は、熊本県山都町(やまとちょう)にある歴史的な石橋で、江戸時代に建設され、現在もその美しい姿を保っています。水路橋として有名で、農業用水を供給するための重要な役割を果たしてきました。また、通潤橋は、日本の土木技術の粋を集めた建築物としても高く評価されています。 1632年に着工され、1635年に完成しました。橋を築いたのは、細川忠利という人物で、当時の熊本藩の藩主でした。彼は、農業用水の供給を目的とした水路の整備を進め、通潤橋はその一部として建設されました。 当時、山間部での農業用水の確保は非常に重要な課題であり、この橋は水を効率よく流すために設計されたものでした。通潤橋は、石造りのアーチ橋として建てられ、橋の中央に水を通すための水路が設けられています。これにより、周辺の農地に必要な水を供給することができました。 最大の特徴は、その独特なアーチ構造と、水路橋としての機能です。橋は、石積みで造られており、非常に頑丈で美しいデザインが施されています。アーチは、物理的に圧力を分散させる役割を果たし、長年にわたって安定性を保っています。 また、上部には、水路のための穴があり、これによって橋を通過する水流が直接橋の上を流れるようになっています。この水流は、農業用水を農地に供給するための重要な機能を持ち、そのため地域の農業にとって欠かせない存在だったそうです。 現在も観光名所として多くの人々に親しまれています。周囲の自然環境との調和が美しく、訪れる人々はその雄大な景色に感動すると思います! 通潤橋には橋の上を歩ける道があり、訪れる人々はその歴史的な遺産を間近で見ることができます。定期的にライトアップが行われ、夜間でもその美しいアーチのシルエットを見ることができるため、夜景も人気があります。 歴史的価値だけでなく、日本の土木技術や建築美を感じることができる場所としても重要です。日本の重要文化財にも指定されており、地域の歴史や文化を学ぶ場としても機能しています。さらに、周囲には自然散策路や温泉地、地元の特産品を販売する市場もあり、観光地としての魅力も多彩ですので一度自然を感じに行かれてみてください(^^)
-
周辺施設山都通潤橋ICから下記の施設まで直線距離で914m
五老ヶ滝
所在地: 〒861-3661 熊本県上益城郡山都町長原
- アクセス:
桜町バスターミナル-通潤山荘・田迎・御船経由「「通潤山荘」バス停留所」から「五老ヶ滝」まで 徒歩4分
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 上益城郡山都町にある最大級の滝です。 高さ50メートルから一直線に落下する迫力満点の滝です。 展望所にある駐車場から物凄い音が聞こえ、石段を降りること役10分。 大量のしぶきをあげながら、一直線に流れ落ちる滝は大迫力です! 更に降りて行くと吊り橋があり、橋の上から全景を一望できます。 迫力がありすぎて、吸い込まれそうになりますが気持ちいいです。
-
周辺施設山都通潤橋ICから下記の施設まで直線距離で935m
布田神社
所在地: 熊本県上益城郡山都町長原
- アクセス:
桜町バスターミナル-通潤山荘・田迎・御船経由「「通潤山荘」バス停留所」から「布田神社」まで 徒歩2分
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 熊本県上益城郡山都町長原219に位置する布田神社は、昭和11年11月創立、ご祭神は第16代矢部手永惣庄屋である布田保之助(享和元年(1801)11月26日生)が、天保4年(1833)2月矢部手永地区の惣庄屋となり、嘉永7年(1854)閏7月29日通潤橋の通水管(吹上樋)1本の通水に成功されてます。同年8月晦日通潤橋の渡り初めが実施されました。文久元年(1861)に隠居、明治6年(1873)4月3日に亡くなられています。今年この通潤橋が国宝に指定されることとなった為、参拝客が徐々に増えてます。また、案外知られていませんが、実は布田神社はここ以外にもう1箇所町内にあるそうです。島木の峰という集落の高台に祭られており、峰の布田神社のすぐ下には、通潤橋架橋2年前に完成した中島福良井手が通っているそうです。これも布田翁が手掛けられた井手とのことです。 2年前と言っても通潤橋架橋に1年8ヶ月を要しているので、中島福良井手が完成してすぐに通潤橋の工事に着手している。この間に、吹上樋の実験もしている。そればかりではない。布田翁は、他の井手や道路などの多くの工事も同時並行して行っておられることになります。まさしく神業ですね。境内地内には、通潤橋架橋に関するいろんな記念碑が建立されていますが、その多くが平成28年4月の熊本地震により倒壊しました。 通潤橋の国宝指定に向けて地元も盛り上がっています。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 通潤橋は、熊本県山都町(やまとちょう)にある歴史的な石橋で、江戸時代に建設され、現在もその美しい姿を保っています。水路橋として有名で、農業用水を供給するための重要な役割を果たしてきました。また、通潤橋は、日本の土木技術の粋を集めた建築物としても高く評価されています。 1632年に着工され、1635年に完成しました。橋を築いたのは、細川忠利という人物で、当時の熊本藩の藩主でした。彼は、農業用水の供給を目的とした水路の整備を進め、通潤橋はその一部として建設されました。 当時、山間部での農業用水の確保は非常に重要な課題であり、この橋は水を効率よく流すために設計されたものでした。通潤橋は、石造りのアーチ橋として建てられ、橋の中央に水を通すための水路が設けられています。これにより、周辺の農地に必要な水を供給することができました。 最大の特徴は、その独特なアーチ構造と、水路橋としての機能です。橋は、石積みで造られており、非常に頑丈で美しいデザインが施されています。アーチは、物理的に圧力を分散させる役割を果たし、長年にわたって安定性を保っています。 また、上部には、水路のための穴があり、これによって橋を通過する水流が直接橋の上を流れるようになっています。この水流は、農業用水を農地に供給するための重要な機能を持ち、そのため地域の農業にとって欠かせない存在だったそうです。 現在も観光名所として多くの人々に親しまれています。周囲の自然環境との調和が美しく、訪れる人々はその雄大な景色に感動すると思います! 通潤橋には橋の上を歩ける道があり、訪れる人々はその歴史的な遺産を間近で見ることができます。定期的にライトアップが行われ、夜間でもその美しいアーチのシルエットを見ることができるため、夜景も人気があります。 歴史的価値だけでなく、日本の土木技術や建築美を感じることができる場所としても重要です。日本の重要文化財にも指定されており、地域の歴史や文化を学ぶ場としても機能しています。さらに、周囲には自然散策路や温泉地、地元の特産品を販売する市場もあり、観光地としての魅力も多彩ですので一度自然を感じに行かれてみてください(^^)
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 熊本県上益城郡山都町長原219に位置する布田神社は、昭和11年11月創立、ご祭神は第16代矢部手永惣庄屋である布田保之助(享和元年(1801)11月26日生)が、天保4年(1833)2月矢部手永地区の惣庄屋となり、嘉永7年(1854)閏7月29日通潤橋の通水管(吹上樋)1本の通水に成功されてます。同年8月晦日通潤橋の渡り初めが実施されました。文久元年(1861)に隠居、明治6年(1873)4月3日に亡くなられています。今年この通潤橋が国宝に指定されることとなった為、参拝客が徐々に増えてます。また、案外知られていませんが、実は布田神社はここ以外にもう1箇所町内にあるそうです。島木の峰という集落の高台に祭られており、峰の布田神社のすぐ下には、通潤橋架橋2年前に完成した中島福良井手が通っているそうです。これも布田翁が手掛けられた井手とのことです。 2年前と言っても通潤橋架橋に1年8ヶ月を要しているので、中島福良井手が完成してすぐに通潤橋の工事に着手している。この間に、吹上樋の実験もしている。そればかりではない。布田翁は、他の井手や道路などの多くの工事も同時並行して行っておられることになります。まさしく神業ですね。境内地内には、通潤橋架橋に関するいろんな記念碑が建立されていますが、その多くが平成28年4月の熊本地震により倒壊しました。 通潤橋の国宝指定に向けて地元も盛り上がっています。
- 前のページ
- 1
- 次のページ
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本